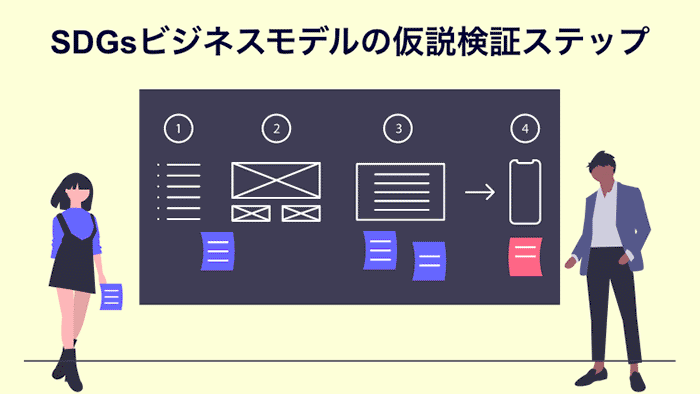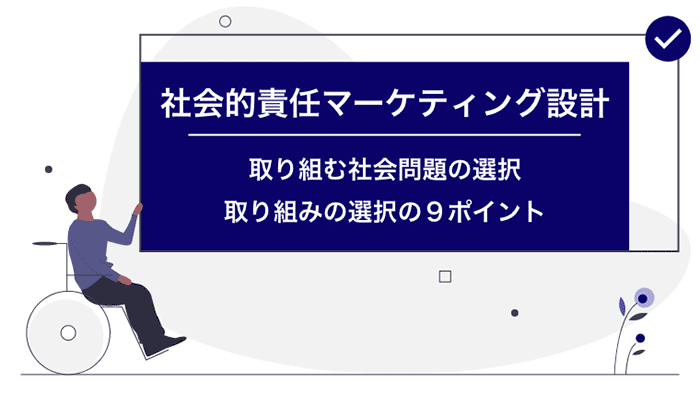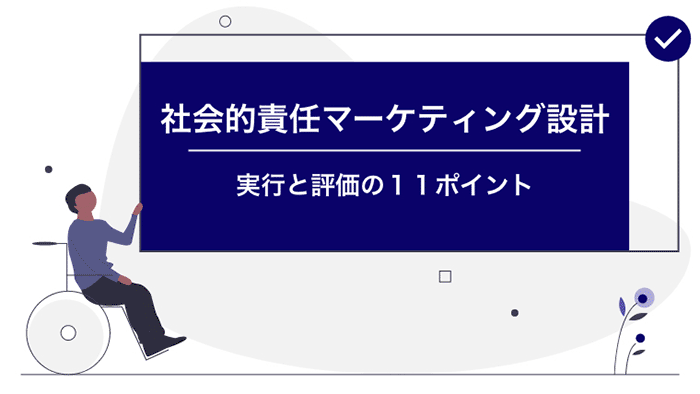こんにちわ。ソーシャルビジネスを日本に広めたい南(@minami_shiroInc)です。
SDGsをはじめとした社会問題を何とかビジネスで解決していきたいと考えている人向けに、どのような競争戦略をとり、SDGs(ソーシャル)ビジネスモデルをどのように開発し、開発したビジネスモデルをどのように仮説検証していけばよいかを、1万文字以上で解説した。
とても長いので、実際にアクションする際に、必要な箇所のみを読み返すように使っていただければ幸いだ。
目次
これまでのSDGs経営変革ロードマップおさらい
これまでSDGsを経営に統合させるためのロードマップとして、まずはビジョン(大義)を創り、戦っていくフィールドを決めてきた。
経営者必見!SDGsを経営に統合する変革を起こすためには必要なビジョンメイキングとは?
自社がSDGs経営/ビジネスを展開するバトルフィールドを選ぶ方法~サスティナビリティ観点でのクロスSWOT分析~
バトルフィールドを決めるために、17の目標/169のターゲット/244の指標をレビューしたり、バリューチェーン全体で自社への正負の影響を評価したりしてきた。
そして、国際<IR>フレームワーク(*1)で紹介されている6つの資本をベースにクロスSWOT分析をして、自社の強み弱み/チャンスとリスクを明確にし、戦略の方針を決め、最終的に戦うフィールドを選定した。
- 財務資本
- 製造資本
- 知的資本
- 人的資本
- 社会関係資本
- 自然資本
続いては、戦うフィールドで具体的にどのように勝っていくかを考えていく。
ターゲットのニーズに応えつつ、社会問題を解決していくためのビジネスモデルを創っていく必要がある。
どのような戦略をとり、これまで情報を集めて分析した内容をもとに、どうビジネスモデルを創り、仮説検証していくかのステップを詳細に解説していく。
ソーシャルビジネス,SDGsビジネスといわれる事業を創るまでの研修/コンサルティングを実施するプレイヤーは市場に出てきた。ここでは、ビジネスモデルを創り、仮説検証した後に関係してくる「社会的責任マーケティング」についても触れる。
本記事を読んでくださった方にとって、既存事業のブラッシュアップ、新規事業づくりのお役に立てることを願う。
それでは、解説していく。
SDGsビジネスで選択すべき競争戦略とは?
SDGsに向けた取組みが今までのようなCSR活動の延長線上で終わらないためにも、ビジネスで社会問題解決できるロジックを明確にして、戦略をつくる必要がある。
競争優位を見出す戦略といえば、マイケル・ポーターさんの「3つの基本戦略」が有名だろう。
知っている人もいるだろうが、サクッと振り返っておこう。
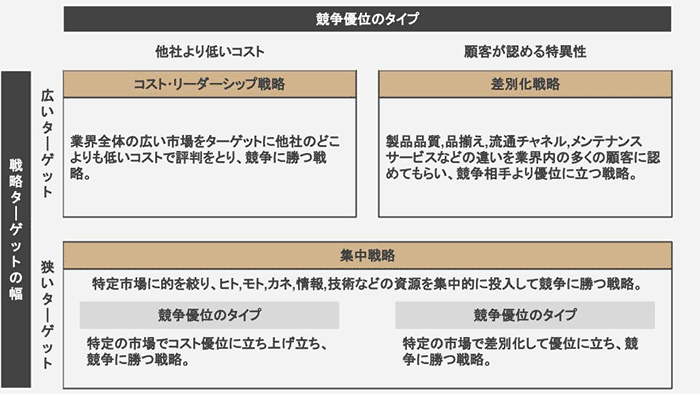
(出所:M.E.ポーター『(新訂)競争の戦略』ダイヤモンド社、ヘンリー・ミンツバーグ,ブルース・アルストランド,ジョセフ・ランペル『戦略サファリ(第2版)』東洋経済新報社よりSHIRO作成)
◆コスト・リーダーシップ戦略
業界全体に対して幅広いターゲットを狙いつつ、競争相手よりも圧倒的な低コストで優位に立とうとする戦略だ。
競争相手と同じ商品・サービスだったとしても、最も低コストで提供していくことを目指す。
ここで注意してほしいのは、「最も安く売る」ことではない。「最も低い原価/費用」で競争相手と戦っていくことである。
◆差別化戦略
幅広いターゲットを狙いつつも、低コストではなく、競争相手の商品/サービスとは違ったユニークな価値を創り出して優位に立とうとする戦略だ。
品質,品揃え,流通チャネル,オプションのサポートサービス,使いやすさなどを差別化し、価格の高さを正当化することを目指す。
◆集中戦略
コストと差別化ポイントのどちらかに集中して、狭いターゲット内で競争相手よりも優位に立とうとする戦略だ。
国際<IR>フレームワークで紹介されているような6つの資本を「低コスのト実現」or「差別化ポイントの実現」のどちらかに集中させていく。
もちろん、「差別化ポイントの実現=>低コストの実現」の順に資本を集中させていく中長期的な戦略をつくるケースもある。
さて、競争相手よりも優位に立ち、ビジネスでSDGs達成を目指すために採るべき戦略は差別化戦略だ。
低コストなサービスを実現させる必要もゆくゆくは必要だが、まずは競争相手が未だ成し遂げられていない差別的な事業を構築し、業界ルールを破壊していかないと社会問題を解決することは困難だ。
むしろ、競争相手が行っている事業で社会問題が解決するのであれば、それは競争相手に任せて、違う社会問題に対して向き合うことが、総括的にSDGs達成実現に近づく道ではないだろうか。
差別化戦略をつくるためのアクション方法
さて、差別化戦略をつくるためにどんなアクションをすればいいかを述べていく前に、「差別化」の大前提について数行でお伝えしておく。
差別化とは、めちゃくちゃシンプルにいえば「他社と違うことをしよう」って話だ。
しかし、ただ違うことをすればいいって訳じゃない。
たとえば、サッカーボールを販売している会社がライバル企業に勝つために、トゲトゲのサッカーボールをつくって差別化しようとしたとしよう。
このトゲトゲサッカーボールは売れるだろうか?
誰も売れないと考えるだろう。そりゃそうだ。
トゲトゲサッカーボールは、サッカーボールの基本的な役割である「蹴れる」「地面を真っ直ぐころがる」などを満たせていないので売れる訳がない。
(トゲトゲしていても蹴れるよ!と気合のはいった人はいったんスルーする…)
つまり、顧客体験価値をそこなう差別化をしても意味がないのだ。
この例えだと当たり前だと思う人もいるだろうが、意外と同じような差別化をしてしまっている企業がいる。
差別化の大前提は、「顧客体験価値を向上させられる差別化の要素」を生み出すこと。
肝に命じておこう。(私自身にも言っている)
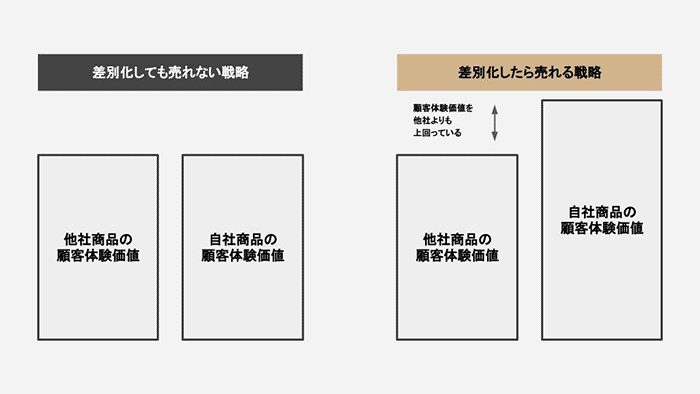
差別化のための4つのアクション
差別化の要素を考えるアクションの方針は4つだ。
- 増やす
- 付け加える
- 減らす
- 取り除く
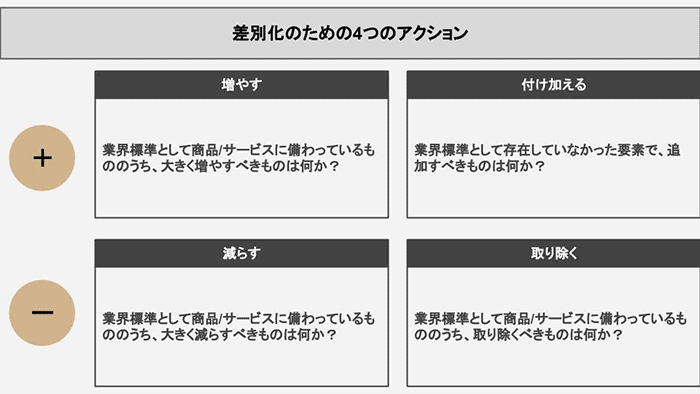
(出所:W.チャン・キム,レネ・モボルニュ『ブルー・オーシャン戦略』よりSHIRO作成)
これら4つの方針を組み合わせたりもしつつ、差別化していく方針を考えていく。
次に「何を」増やしたり、減らしたりすればいいかを伝える。
商品・サービスだけではなく、事業全体に広げた際にどんな切り口で4つのアクションをすればいいかの要素を書き出しておく。
- マーケット(海外に販売するなど)
- 用途(同じ商品を別の用途に合わせて再開発するなど)
- 性能(他社にはできない性能を付け加えるなど)
- 品揃え(他社とは違った商品・サービスを用意するなど)
- サイズ(他社製品よりも極端に小さくするなど)
- 機能(課題解決できる業界初の機能を開発するなど)
- 使いやすさ(1つの機能に絞るなど)
- 評判(特定の人や企業からの評判を高めて口コミ効果を最大化させるなど)
- 地域(他社が進出していない土地に進出するなど)
- デザイン(他社よりもカラーバリエーションを増やすなど)
- 売り方(同じ商品だとしても朝専用商品として売り出すなど)
- 価格(他社製品と同じクオリティで安くするなど)
- 流通チャネル(販売する場所を特化させるなど)
- タイミング(3歳の子ども向け商品を妊娠している人にも提供するなど)
- NPO法人・企業・公的機関などとの関係性(パートナーを増やして共同販売するなど)
- 取り組む社会問題(環境問題だけでなく貧困問題にも取り組むなど)
- 収益モデル(当事者からではなく企業からマネタイズするなど)
これらの切り口をもとに、他社がしていない、もしくは日本企業全体がしていないあなたのいる会社ならではのSDGsビジネス開発にチャレンジしていこう。
(わたし達も全力で精進する)
社会問題解決に向けたビジネスモデルを検証するまでのステップ
具体的ににどうビジネスモデルを開発して、マーケットフィットするか、収益モデルが成り立つかを検証するまでのステップを述べていく。
①SDGsに代表される社会問題を軸にした事業機会のリサーチ&検討
まずは、社会問題を軸にした事業機会をリサーチし、どれから取り組むか検討する。
「バトルフィールド」でもやっていることだが、あらためてSDGs17目標、169ターゲット、244指標の関連するところをみかえしてインプットしなおそう。
参考:SDGsって言葉だけ聞いたことある人向け!169個のターゲットがあります
続いて、選定したバトルフィールドに属する当事者の課題やその社会問題の構造をリサーチして理解していこう。
新規事業で重要なことは「顧客の課題」を特定してから商品/サービス作りを始めること。
起業家兼コンサルタントをしているダイアナ・キャンダーが書き全米70校で教科書として使われている『STARTUP アイデアから利益を生み出す組織マネジメント』では、以下の順序が重要だと述べらている(*2)。
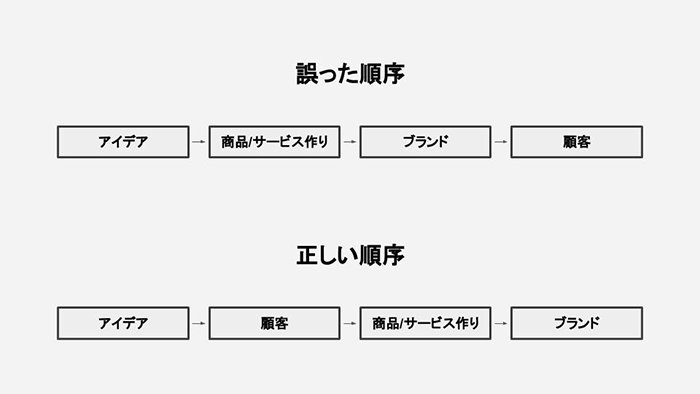
(出所:ダイアナ・キャンダー『STARTUP アイデアから利益を生み出す組織マネジメント』よりSHIRO作成)
バトルフィールドを選定するために、いろいろ社内外の情報を整理していると「こんな事業をしたらいいんじゃないか?」とアイデアがぽんぽん湧いてくる人もいるだろう。
しかし、一般的なビジネスでも、SDGs(ソーシャル)ビジネスでも「顧客(当事者)の課題(欲していること)を理解する」のが欠かせない。
課題を検証してからでないと、どんなアイデアが浮かんだとしても、それは水の泡になる。
「いい解決策=いいアイデア」ではないので注意しよう。
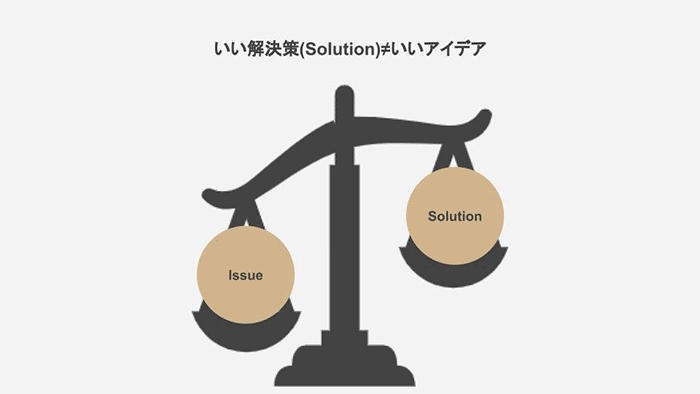
当たり前だが、売れなければ意味がないし、社会問題解決の可能性がなければリソースを割くだけムダになる。
限りあるリソースを活かすためにも、まずは当事者の課題を知ることにリソースを投下しよう。
当事者の課題を特定するためのアクションの例は以下だ。
- 書籍を読む
- 論文を読む
- 当事者に聞く
- 当事者の知り合いに聞く
- 当事者の親族に聞く
- NGOの詳しい人に聞く
- NPO法人の詳しい人に聞く
- 大学教授など研究している専門家に聞く
アクションするのが今すぐには難しい場合もあるはずなので、まずはできるアクションから実行していこう。
実行している内に状況がかわり、例に出したすべてを実行できるようになることもある。
事業の優先順位を決めるために投資家やサプライヤーなどのステークホルダーにもヒアリングしておこう。
以下のような調査(*3)で世論がどの社会問題に関心があるかの数値も出ているので参考にするといい。
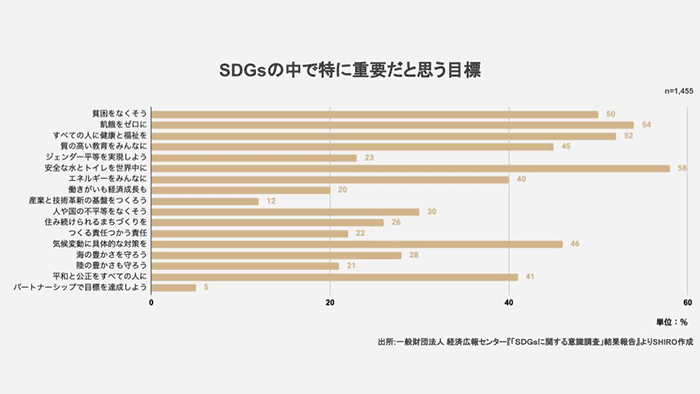
※世論の関心高い社会問題から取り組もうって話ではない
また、既存事業の課題を特定し、その課題解決のために生み出したビジネスでSDGs達成に挑戦しているのが株式会社LIFULLだ。
LIFULLは住宅弱者と言われる方を1人でもなくすために、外国人やLGBTらの方々と親身になってくれる不動産会社をつなぐ取り組みをしている。
詳しい内容はHUFFPOSTさんの「「住宅弱者」がいることを知っていますか? 国籍や性別、貧富の差にかかわらず、誰もが住まいを選べる世界の作り方とは」が素敵すぎるので読んでみてほしい。
課題のリサーチや検証をし、事業機会を検証した後は、具体的な優先順位を決めていくステップだ。
②クロスSWOT分析結果を軸にした取り組む事業の優先順位づけ
課題(Issue)を特定した次は、解決する課題や事業機会の優先順位決めていく。
「バトルフィールド」でサステナビリティの観点でクロスSWOT分析をして内部の強み・弱みを再定義した。
ここの分析情報と自社の親和性が高い解決すべき課題の優先順位を決めていこう。
- 自社らしさがあるかどうか
- 事業創出の参考になりそうな情報があるかないか
- 事業創出する上で相談できる相手が社内外にいるかどうか
- 本当に特定した課題を解決することにビジョンを持てるかどうか
- 情熱をもって事業創出に取り組めるかどうか
などの観点とクロスSWOT分析した結果を踏まえて、最終的にアクションする課題と事業機会を決定させる。
解決すべき課題と事業機会の優先順位を決めたら、SDGs(ソーシャル)ビジネスの収益モデルやソリューションを考えるフェーズだ。
③社会問題解決に向けたビジネスモデルの仮説づくり
取り組む課題に対して仮説をもとにビジネスモデルやソリューションを創る。
まず大前提として、一般的なビジネスでもそうだが、以下のマインドをもって、ビジネスモデルやソリューション創りにとりかかろう。
「儲かる」「創れる」「使ってもらえる」ベン図の真ん中に近いビジネスモデルを心がける
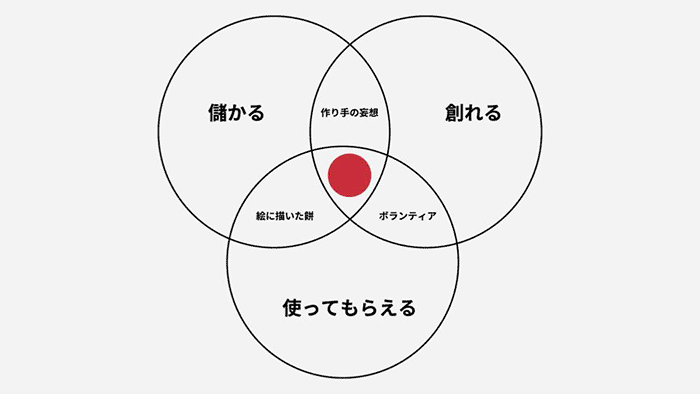
事業創りにおいて、「儲かる」「創れる」「使ってもらえる」のバランスがかなり重要。
どういうことか説明しよう。
①儲かる×創れる
自社技術や他社とアライアンス結んで創れてかつ儲かると考えられるだけの事業は、課題や痛みを抱える人の解決策になってなく、使ってもらえない。
つまり、事業つくり手の妄想ということになる。
②儲かる×使ってもらえる
儲かる上に使ってもらえると考えられる事業は、いっけんよさそうにみえる。
しかし、肝心な「創れるかどうか」の観点が抜けており、当然だが創れなければ世の中にローンチできない。
つまり、絵に描いた餅となる……。
③創れる×使ってもらえる
創れるし使ってもらえると考えられる事業は、課題や痛みを抱える人の解決策になっており、とてもハッピーなことだ。
儲からなければサスティナブルな事業ではない。
ここがSDGs(ソーシャル)ビジネスに挑戦する際の最大の壁だと考えている。
どう儲かるモデルを生み出すか。社内外の人とディスカッションを重ねてイノベーションを起こすことが求められている。
要するに、「儲かって、創れて、使ってもらえる」ビジネスを考えようって話。
容易なことではないが、この前提を抜きに時間やお金を使ってもムダになってしまう。
考える前に、この前提をしっかり頭の中にいれておこう。
ビジネスアイデアをブレストする際にビジネスモデルナビゲーターがかなり使える
ビジネスアイデアを考える上で重要なことは、「アイデアは既存の要素の掛け合わせ」ということ。
ゼロからアイデアをひねり出そうとするのではなく、いま世界にあるビジネスモデルをリサーチしつつ、考えるのが発想の幅も広がれば、比較的はやくよいアイデアが生まれる。
ジェームス・W・ヤング氏の『アイデアのつくり方』が世界中で有名すぎるが、この書籍の中でも以下のように書かれている(*4)。
アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもないということである。
つまり、「既存の要素」または「既存のビジネスモデル」のストックを増やしておくことが、新しいビジネスアイデアを生み出すためには必要だ。
そこで、『ビジネスモデルナビゲーター』がかなり使える。
オリヴァー・ガスマン、カロリン・フランケンバーガー、ミハエラ・チックの3人によって作られた本書では、長年の研究より突き止めた成功する企業が展開しているビジネスモデル55パターンが紹介されている。
この55パターンが1枚ずつカードになった『ビジネスモデル・ナビゲーター 55パターンカード』もローンチされており、複数名でブレストする際にかなり使える。
ちょっとお値段的に買えない人は、自身なりにGoogleスライドなどでパターン別に内容をまとめて、それを印刷してラミネートしたものを使えば十分だろう。
ビジネスモデルナビゲーターで紹介されているビジネスモデルを一部編集したスライド例が以下。



ご要望があれば、自身が経験してきたビジネスモデルも含めた、ビジネスモデルを発想するためのスライドを完成させて、無料で配布する。
「お問い合わせ」や「本記事をシェアしたSNS投稿」から連絡もらえると嬉しいです。
既存のビジネスモデルを掛け合わせつつ、特定した課題を解決できるソリューションを考えまくってみよう。
SHIROの研修メニューの1つである「SDGsビジネスダイアローグ」も取り入れつつ、プロジェクトメンバーで対話型のブレストをするのもおすすめだ。
最後に、具体的に複数の観点でビジネスを構築していく際につかうリーンキャンバスにふれておく。
「パートナー」を加えたリーンキャンバスで高速仮説検証をしよう
ビジネスアイデアの整理でよく使われているリーンキャンバスというフレームワークがある。
リーンキャンバスとは、『リーンスタートアップ』で有名な起業家のエリック・リースから応用されたビジネスモデルを1枚の図に整理するフレームワーク。
これにSDGs17「持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する」にもあるように、「パートナー」を追記したフレームワークで複数のアイデアをビジネス観点で整理し、PDCAサイクルを回せるようにしよう。

SDGs(ソーシャル)ビジネスの創出では「パートナーシップ」が重要である。
SDGsでわざわざ目標にされていることからもわかるように、ビジネスでの社会問題解決には、資金、技術、知恵、問題理解の深さ、ネットワーク、人的リソースなどが必要なため、自社だけではなくパートナーとの共創がカギだ。
そのため、リーンキャンバスの「独自の価値提案、圧倒的な優位性、コスト構造、収益の流れ」を考える際に、自社だけで実行する前提でもいいが、パートナーとの共同事業の前提も頭においておくのが必要。
- 自社のみ
- 1社との共同
- 複数社との共同
- NGO/NPO、企業との共同
など複数パターンでブレストするのもいいだろう。
④プロトタイプカンバンボードを土台に仮説検証体制創り&実行
ここまでに課題の検証、リーンキャンバスによるビジネス案づくりについて説明してきた。
特定したプロブレムと想定しているソリューションが合致する状態(プロブレム・ソリューション・フィット)を目指すために、これまでに整理した情報をもとにプロトタイプカンバンボードをつくっていこう。
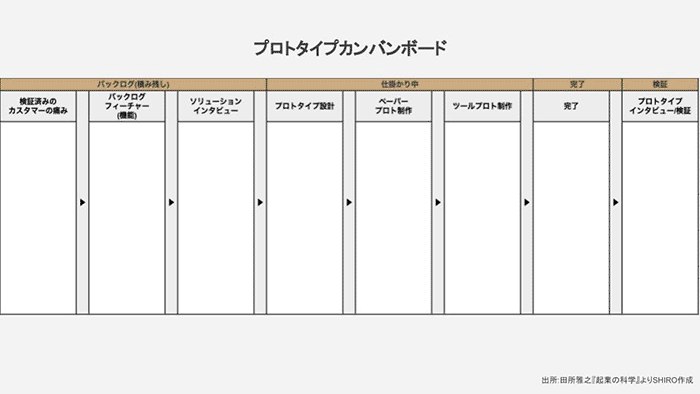
プロトタイプカンバンボードは、ソフトウェア開発でよく使われる解決策を磨き込むためのフレームワークだ。
ビジネス創り(プロジェクト)の進捗を見える化して、チームで「いまどの課題に取組み、どの機能にフォーカスして、プロトタイプの検討がどれくらい進んでいるか」を共有する。
簡単にプロタイプカンバンボードについて説明していく。
主にアプリケーションやウェブサービスなどの開発を前提にしている。
ただ、オフラインのサービス開発でも使える点が多くあるので、サクッと読んでほしい。
1.検証済みのカスタマーの痛み
「SDGsに代表される社会問題を軸にした事業機会のリサーチ&検討」で特定したターゲット(カスタマー)の課題(痛み)を書き出そう。
2.バックログフィーチャー(機能)
ここには、「どのような価値をどのように製品やサービスに実装するか」を書き出そう。
つまり、どのような価値や体験を備えたソリューションをターゲットに提供するかを明確にする。
たとえば、「貧困世帯の高校生に、ITスキル獲得の機会を得られるインタラクティブなオンライン学習ツールを提供する」などだ。
- どのようなソリューションだったらターゲットの課題を解決できるか
- どのような機能がある製品だったらターゲットの課題を解決できるか
の問に対して何度もプロジェクトメンバーとディスカッションし、出てきたアイデアを書き出そう。
3.ソリューションインタビュー
ここでは、ソリューションが本当にターゲットの課題を解決できるかをターゲットやターゲットを熟知した人にインタビューした内容を書き出していく。
SDGs(ソーシャル)ビジネスの場合、ターゲット本人にインタビューできる機会をつくるのが難しい時もある。その場合は、関わりのあるNGO/NPO法人のスタッフ、大学教授、社会活動家などにインタビューさせていただく機会をつくってもらえいないか交渉しよう。
(ターゲット本人にインタビューするのがベストだが……)
具体的にどうやってインタビューするかは、元シリコンバレーVCパートナー、ユニコーンファームCEO、ベーシックCSO、関西学院大学客員教授などを務める田所雅之さんの『入門 起業の科学』から引用する(*5)。
解決策を示さず、想像の世界で本音を引き出すために「魔法のランプ」という質問法を使います。
ソリューションインタビューの質問リスト
- 魔法のランプがあって何でもできるとしたら、【目的とする作業】を完遂するために何をしたいと思いますか?
- その魔法のランプに必ず含まれるべき機能は何だと思いますか?
- そういった魔法のランプに一番近いソリューションや代替案はありますか?
- その代替案の良い点と不足点は何ですか?
- あなたはその魔法のランプを使うとどれくらいの時間や労力などのリソースを節約できると思いますか?
- そういった魔法のランプに対して、どれくらいの予算を確保できますか?
- ここまでできれば感動するというプロダクトのイメージはありますか?
- では、そのプロトタイプができたらまたお会いして、色々とお聞きしてもよいですか?
ソリューションインタビューのチェックリスト
- インタビュー相手は魔法のランプをどう表現したか?
- 魔法のランプを表現した時に身を乗り出していたか?
- 魔法のランプの機能をどう表現したか?
- その魔法のランプは技術的に実現可能か?
- もっと妥当な魔法のランプの代替案は存在しないのか?(インタビュー相手は見落としているだけではないか?)
- もしその魔法のランプを作れたとして、インタビュー相手がその製品を買ったり、使ったりすることを阻む障壁はあるか?(コスト、メンテナンス、習得の難しさなど)
- 魔法のランプは日々の生活や業務の中にフィットした形で使えるだろうか?
- もしカスタマーが魔法のランプを買わないのであれば、どのような理由だろうか?
魔法のランプ質問法をそのまま使える訳ではないが、貴社が考えるソリューションのターゲットにインタビューする際にかなり参考になるので頭の片隅に置いておくといいだろう。
4.プロトタイプ設計
プロトタイプとは、「試作品」「最終的なプロダクトの中~高程度での表現物」を指します。
ソリューションをいきなり完成させるのではなく、プロトタイプ(試作品)をつくり、再度ターゲットにインタビューするのがこの後のステップ。
プロトタイプの種類は様々だが、主に3つある。
1.ファンクショナルなプロトタイプ
「こうやって動く」を検証するためのプロトタイプ。
ペーパープロトタイピングや、InVisionなどのツールを使って、動作のシミュレーションをする。
2.デザインプロタイプ
Adobe XD,figma,Adobe Photoshopなどを使って、見た目を完成品に近づけていくプロトタイプ。
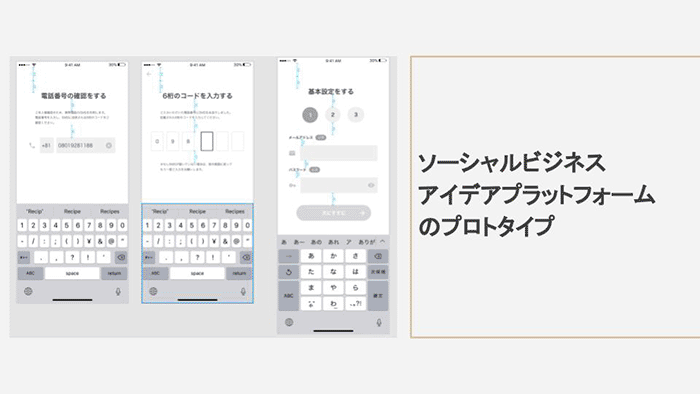
Re:melosマガジンを運営するSHIROが2020年にβ版をローンチする「日本全国の人でソーシャルビジネスのアイデアを創出するプラットフォーム」のデザインプロトタイプはこんな感じ。
(開発がんばります!β版ローンチしたらぜひ使っていただきフィードバックいただけると幸いです)
3.コンテクスチュアルなプロトタイプ
製品やサービスの動画(プロモーションビデオなど)をつくって、ターゲットに製品を実際どう使うのか、どんな体験ができるのかを擬似体験してもらうためのプロトタイプ。
より具体的な問題、改善点を明確にし、製品やサービスの強みを考え直すために用いる。
プロトタイプの種類をまず紹介したが、プロトタイプを設計するフェーズでは、まずユーザー体験(UX)に関する目的別の機能や画面遷移、導線などを整理していく。
アプリケーションではなく、オフライン完結型のサービスの場合、提供するサービス内容と具体的な手法、どの順番でサービスを提供するかなどを整理していく。
一応、プロトタイプをつくっていくのに便利なサービスを載せておく。
5.ペーパープロトタイピング制作
プロトタイプの設計が終わったら、手軽に複数のパターンを形にできるペーパープロトタイピングをつくっていく。
紙とペンをつかって、設計した機能を実際の画面比率などにあわせて形にしていく。
白紙に具体的な形を書いていくのもいいが、プロトタイプ制作ツールの「Marvel」から無料のプロトタイプ用紙が提供されている。
このようなフォーマットを印刷して、ペーパープロトタイピングを制作していくのも一つだ。
また、より実際に近い形を表現するために、モバイルのスクロール機能を想定したペーパープロトタイピングも紙で表現できる。
ペーパープロトタイプを複数パターン制作して、プロジェクトメンバー内で何度も何度もディスカッションして、よりアイデアを洗練していこう。
ちなみに、ペーパープロトタイプの利点は以下。
- 数分で複数パターンのデザインをつくれる。
- 紙とペンがあれば制作できるので安い。
- 制作するのに特別な技術がいらないため、誰でも制作できチームビルディングにもなる。
- やってみると分かるが、中々楽しい(笑)。
6.ツールプロトタイプ制作
ペーパープロトタイプを制作した次は、ツールプロトタイプ(インタラクティブモックアップ)を制作しよう。
ペーパープロトタイプでは分かりにくかったUI(ボタンの配置や大きさ、フォントの大きさや余白など)を調整していく。
ツールプロトタイプをつくることで、ユーザーインタビューした際により具体的で有益なフィードバックをもらえるのでおすすめ。
- マニュアルがなくても直感的に使えるか
- よく使う機能が2秒以内に分かるレイアウトか
- 全ページでボタンの形状が一緒などデザインに一貫性があるか
- ユーザーが動作をやり直せる仕様になっているか
などの点をチェックしつつ、ツールプロトタイプを作っていこう。
7.完了
ペーパープロトタイプ、ツールプロトタイプをつくり終えたアイデアを書き出して、チーム内で進捗を共有できるようにしておこう。
8.プロトタイプインタビュー/検証
ツールプロトタイプつくり終えたら、再度ターゲットにユーザーエクスペリエンス(UX)に関するインタビューをしよう。
またしても、かなり参考になるのでユーザーインタビューの質問リストやポイントを、田所雅之さんの『入門 起業の科学』から引用する(*6)。
プロダクトインタビュー質問リスト
- これは何をするものだと思いますか?
- 今、何をしようとしていますか?
- XXXとう文言をどう解釈しますか?
- XXXボタンは何をするものだと思いますか?
- 次は、何をしますか?
- XXXボタンは期待通りに動きましたか?
- 期待通りでないならば、どのように動くと期待していましたか?
- こういったソリューション(プロダクト)を導入する際に、必然的に伴ってくる費用はありますか?(新しい備品、トレーニングなど)
プロダクトインタビューのチェックポイント
- 「今すぐこれが欲しい」という反応があったか?
- そのプロトタイプを使っていて何かつまずいたことはあったか?
- 課題を解決できる実用上最小限の製品(MVP)の姿を明確にできたか?
- ユーザーがUXによって何を助けてほしいか、どのような体験をしたいかについて(作り手側が)言語化できたか?
さらに深ぼった質問は、ハーバード大学の「 starter questions for user research」を参照するとよい。
初めてユーザーインタビューする方向けに、私も参考にしている有益な記事をいくつか掲載しておくので、参考にしてみるといい。
- UXデザインにおけるユーザーインタビューとは?方法・種類・実例ノウハウ集 | Goodpatch Blog
- THE GUILD勉強会 -ユーザーインタビュー設計-レポート
- 失敗から学んだ、ユーザーインタビュー23の心得 | Goodpatch Blog
- UXデザインに必要なユーザーインタビューの方法と質問設計 | UXデザイン会社Standardのブログ
- ユーザーインタビュー結果を、サービス開発・改善に取り入れるために | Goodpatch Blog
(みて分かる通り、GoodpatchさんがUX/UI領域ではかなり参考になる。個人的に好きな会社さん)
体系的な知識を得たい人は私が読んだこの2冊が参考になった。
ユーザーインタビューをはじめよう ―UXリサーチのための、「聞くこと」入門
マーケティング/商品企画のための ユーザーインタビューの教科書
SDGs(ソーシャル)ビジネスの場合、「共創」がキーポイントだと前述した。プロダクトインタビューする前後で共創相手とも必ずディスカッションを何度もしておこう。
NGOなどの社会課題エキスパートだからこその視点で有益なフィードバックを得られるだろう。
最後に念のため、伝えておく。
プロトタイプカンバンボードと聞くと、Webサービスやアプリ開発の話だけだと考える人がいるが、学習塾などのオフラインビジネスでも同じステップで事業の仮説検証をしていく。
ぜひ、前述してきたステップを抽象化して、事業の仮説検証に役立てて欲しい。
仮説検証後に必要になる社会的責任マーケティング(通称:ソーシャルマーケティング)
何のビジネスにおいても、マーケティングは欠かせない。
ピーター F. ドラッカーさんが、企業のあり方について以下のような洞察をしている(*7)。
企業の目的は,顧客を創造し維持することにある。したがって、企業には2つの、2つだけの基本機能がある。それがマーケティングとイノベーションである。
どの企業、SDGs(ソーシャル)ビジネス問わず、ビジネスをしていく上で、この考え方は非常に大事だと私は考えている。
ある課題を抱えている人が幸せになれる体験を生み出すイノベーション、売れる仕組みを創るマーケティングが企業の根幹である。
SDGs(ソーシャル)ビジネスでも、やはりマーケティングが必須だ。
マーケティング理論はいくつもあるが、その中でも私は「社会的責任マーケティング(通称:ソーシャルマーケティング)」がSDGs(ソーシャル)ビジネスで密に関わってくる概念だと捉えている。
本記事で解説したように、まずはビジネスモデルを開発し、仮説検証をしていく必要があるが、その後はマーケティングが欠かせないので、必要な方は読んでおいてほしい。
SDGs・サスティナブル時代に必要な社会的責任マーケティング(ソーシャルマーケティング)とは?体系的に解説した
【参考・引用】
*1:国際統合報告評議会(IIRC).国際統合報告フレームワーク 日本語訳,13−14.
*2:ダイアナ・キャンダー(2017).STARTUP 利益を生み出す組織マネジメント,17
*3:一般財団法人経済広報センター(2019).「SDGsに関する意識調査」結果報告
*4:ジェームス・W・ヤング(1988).アイデアのつくり方,28
*5:田所雅之(2019).入門 起業の科学,140−141
*6:田所雅之(2019).入門 起業の科学,161−162
*7:Drucker, P. F., (1954) The Practice of Management: A Study of The Most Important Function in American Society,Harper & Row