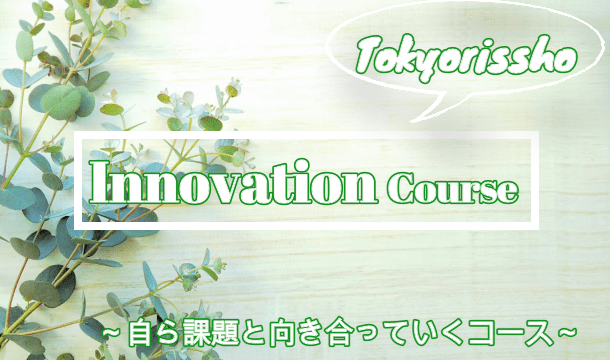耕作放棄地や災害で流通に回せられなかった農作物などをリザインする、社会起業家を排出するプラットフォームなどをてがけるDesign Company株式会社。
東日本大震災をきっかけに、社会課題をビジネスで解決する取り組みを始めた代表の柳岡宏一さんに、これから日本の社会課題を解決していくために必要なこと、各事業の根幹にある理念、今後世界や日本にどのようなアクションをしかけるのかを伺った。(全2回)
第1回:社会課題をリデザインするDesign Companyの挑戦!社会課題との新しい向き合い方を提示する
第2回:気付いたら社会貢献になっているソーシャルビジネスで社会課題解決のインフラを創るDesign Companyの構想

大学時代から何千人規模の学生団体を運営。
3.11をきっかけに独立をし、様々な教育活動を行う。
独立行政法人「国立青少年教育振興機構」管轄プロジェクト2014ミクロネシア諸島自然体験交流事業を担当。
NPO法人自然体験活動推進協議会にて、約100名に対し指導者養成と指導資格発行。
宿泊型研修事業の運営コンサルティングを行う。
その後、健康教育分野での販売コンサル事業で創業。
多くの事業家を輩出し、5億から20億へ成長させる。
『事業とは世の中の困りごとを解決すること』という想い
志に燃える人さえいれば、社会課題を新しい価値へと生まれ変わらせることができるという想いを元に、Design Company株式会社を創業。
課題先進国の日本だからこそ先陣を切って果たせる役割があると考え、日本が抱える課題を新しい発想と表現で解決し、他国のロールモデルとなること、また他国が困った時に「日本はこうやって解決したよ」と解決策を共有し、国と世代を超えて徳を積む事業創出に力を入れている。
社会課題に対してアクションする人を増やすには“キャロットケーキ”がカギ
私たちは事業を始めた時から、“キャロットケーキ”の概念を大事にしています。
みんなケーキは食べますよね。チョコレートケーキ、チーズケーキ、ショートケーキなど。
でも、「健康にいいからニンジンを食べろ」と言っても、「いや、ニンジンあまり好きじゃない……」とニンジンが苦手な人もいるじゃないですか。ところが、キャロットケーキなら食べる人もいるんですよね。
ケーキ屋にキャロットケーキを置いておけば、一定のニンジンが苦手な層をとれるんですよ。「ベイクドチーズケーキ食べあきたから、今日はキャロットケーキを食べてみようかな」みたいに。
それで、キャロットケーキを食べてみておいしかったら、また食べて、徐々に馴染んでくるんですよ。
これと同じように、多くの人が待機児童・貧困などの社会課題を重く受けとめすぎて、問題に取り組んでいる人に対して苦手意識をもったり、他人事になったりしています。
そうしている人たちが悪いわけではなくて、あらゆる人で社会課題に取り組むためには、すでに取り組んでいる人たちが、ディープなものをフラットに見せて活動内容などを発信していく必要があるんじゃないですかね。
 (「ディープなものをフラットにみせる」わかりみが深い…)
(「ディープなものをフラットにみせる」わかりみが深い…)
なので、キャロットケーキとして何をテーマにして、社会課題などの困りごとをディープな見せ方からフラットに見せていくかが大事な気がしているんですよ。
社会課題を無くそうとするのではなく、新しい向き合い方をデザインしていく
私たちが、「Design Company」という社名(言葉)の会社を創った理由は、“社会課題をリデザインする”のが理念だからです。
社会課題ってなくならないと思うんですよ。社会課題をなくそうとするのではなくて、向き合い方を提示していく必要があると思っています。
例えば、僕はヘルニアです。ヘルニアの問題をなくすことがソリューション(解決策)だと思うじゃないですか。すると、手術などがソリューションだと思うのですが、実際に治るかどうかは難しい。どんなに医療が高度になっても、ヘルニア人口はゼロにならないと思います。
つまり、社会課題はなくならないんですね。
 (柳岡さんヘルニアらしい…ヘルニアとの向き合い方をもっと知りたかった…)
(柳岡さんヘルニアらしい…ヘルニアとの向き合い方をもっと知りたかった…)
でも、ヘルニアとの上手な付き合い方をWebで配信したら、冬に痛んだ時はこうしてますとか、くしゃみをする時のコツは「ハクション!とすると痛むから、クチュっとする」とか、ちょっとした向き合い方の提示で社会課題を解決できると思うんですよね。
このような、“日常生活のリデザイン”こそが、社会課題を解決することだと考えています。
とにかく“Funny(面白くて楽しい)”が大事
社会課題に取り組む上で、私たちは、とにかく“Funny(面白くて楽しい)”を大事にしています。
なぜなら、私自身が、シンプルにFunnyなことしかしたくないんですよね!(笑)
 (お話している柳岡さん自身がとっても楽しそう!)
(お話している柳岡さん自身がとっても楽しそう!)
それに、人が集まるところにはFunnyがあると思っています。
よく考えてみたら、Mr.Childrenが歌えば、数万・数十万人が集まって、数百万円・数千万円のお金が動きます。でも、私もやってきましたが、NPO法人の人が1日12時間くらい熱心に「募金よろしくお願いします!」と街頭演説しても、集まるのは10万円程度……。
「何なんだこの差は!」と思ったわけですよ。やっぱり、人が集まるところには、楽しくて面白いことがあると思ったので、社会課題に取り組むことを面白く、楽しくリデザインする必要があるんじゃないかと考えるようになりました。
素人だからこそ社会課題に対してできることがある
最近、高校生が受験勉強でよく使っている「スタディサプリ」があるじゃないですか。
教育業界のイノベーティブなサービスのいい事例です。でも、これ創ったのって元から教育問題に取り組んでいた人でしょうか。違いますよね。創ったのはリクルートなんですよ。全然、教育業界とは関係なかった人がイノベーションを起こしたわけです。
つまり、ある業界のイノベーションは元々業界にいなかったプレイヤーが起こすのではないでしょうか。
シュンペーターのイノベーション理論でいう創造的破壊をできる人は、創造できる人、つまり“よそ者・バカ者・若者”だと思います。
この“よそ者・バカ者・若者”が、外から業界に入っていけば、イノベーションが起きると考えています。なので、社会課題解決に関心のなかった人が、ある社会課題の業界に入ってこれる設計を常に心がけています。
また、どの事業を設計するにしても、仲間に「僕たちが素人だからこそ解決できることをやろ!」と言っています。
 (「素人だからこそ解決できること」がとっても心にしみた)
(「素人だからこそ解決できること」がとっても心にしみた)
素人だからこそ、こうした方が良い、ああした方が良いっていうアイデアが出てくると思うんですね。
私たち自身も、素人だからこそできることがあると考え、農業・貧困・子育てなどの複数の社会課題を解決する事業にチャレンジしています。
私たち自身も素人ながらチャレンジしつつ、社会課題に対して素人である“よそ者・バカ者・若者”を社会課題の業界に呼び込むためには、やっぱりFunnyが大事だと思うんです。
社会課題を他人事だと思っている人を生んでいるのは、社会課題に熱狂的な人たち
農業・教育・待機児童などの社会課題を解決する業界に、外から優秀な人が入ってくるためには、“楽しくやっているな”と思ってもらうことが大事だと思うんですよね。
楽しくなくて真面目すぎると、「今さら私がやってもな」「あまり知識のない私が入っても申し訳ない」と思われてしまい、外から人が入ってこなくて、業界が孤立すると考えています。
多くの人にとって、社会課題が他人事化してしまうのは、「熱狂的なファン」の存在が大きいと思います。
例えば、すごく熱狂的な政治応援団体がいて、団体の人が熱狂的に大衆に呼びかけていたとします。すると、「いや、今さら私が政治について取り組んでもなー」「私は同じような熱意をもってやれない」と思われてしまうんです。
このように、社会課題の他人事化を生んでいるのは、実は社会課題を解決しようとしている熱狂的な人だったりするんです。
だからこそ、「楽しそうにやっているな」と思ってもらえて関わってもらい、実は行っていることが社会課題の解決に繋がっているような仕組み・事業が大事です。なので、キャロットケーキですね。だって、頑固な農家さんから適当に野菜買ったら、怒られそうじゃないですか(笑)。「お前らニンジンの選び方もわからんのか!おれはこんなにこだわっているのに!(最近の若者わ!)」って。「すみません!!」て謝るしかないじゃないですか。
とても真面目に取り組みつつも、楽しむ・楽しそうに思ってもらうのが一番ですね。
 (お話を伺っている中で「キャロットケーキ」15回は出た)
(お話を伺っている中で「キャロットケーキ」15回は出た)
社会課題に関わる人の“ハピネスの総量”を最大化させるのがこれからは大事
これからの時代は、“社会課題を解決するプロジェクトの共有”がカギだとも考えています。
少し概念的な話をしますね。
資本主義って、どうしても投資対収益率が最終ゴールなんです。トマ・ピケティが唱えた「r(資本収益率)>g(経済成長率)」を踏まえると、経済が成長すればするほど、投資家に富が集まってしまう式に今の時代はなってしまっています。
 (急にFunnyじゃない話になった…でも、めっちゃ大事な話)
(急にFunnyじゃない話になった…でも、めっちゃ大事な話)
つまり、富が分配されるのではなく、富が集約されていっています。
結局、資本主義は、100万円の収益があったら、それを2人で分ける、10人で分ける、ただそれだけ。いかに関わる人間を減らし、分配先を減らしていくかが前提になっています。
これが良いか悪いかは別として、こういう経済原理に今の時代はなってしまっています。
資本主義社会が関わる人間を少なくし、資本効率を最大化させるだとすると、ポスト資本主義社会(呼び方は何でもいいですが)では、関わる人間を増やし、関わる人の幸福度「GNH(国民総幸福量)」の最大化をしていくことが重要だと考えています。
関わった人のハピネスの総量を最大化していくことこそが、社会課題に関するビジネスの事業価値です。
なので、Design Companyの役割は、社会課題に関するビジネスを通して「関わった人のハピネスの総量を最大化できる」デザインをしていくこと。
日本で生まれたソーシャルビジネスモデルを海外展開していく
Design Companyのゴールは、シンボルとなるようなソーシャルビジネスモデルの辞書を創って、海外に輸出することです。
本じゃなくてもいいんですけど、本にすることで一つのバイブルになると思っているんですね。
日本のいついつにはこういう社会課題がありましたと。それを解決するビジネスモデルとして、こういうプロセスでやりましたと。難しかった壁はこういうところですと。
時代別の社会課題に対するソーシャルビジネスモデルを一冊の本にまとめ、輸出していきます。
 (未来を見据えつつ、今を楽しみつつ、事業展開している柳岡さん…ステキすぎる)
(未来を見据えつつ、今を楽しみつつ、事業展開している柳岡さん…ステキすぎる)
キリスト教の聖書のようなものですね。「隣人を愛しなさい」という教えによって救われた人がいたように、聖書って問題解決バイブルだから世界中に広まったと思うんですね。
ソーシャルビジネスモデル版の聖書を創って、問題解決されるプラットフォームを創っていこうと考えています。
編集後記

これまでに、社会課題を解決しようと取り組んでいる組織に出会ってきたが、Design Companyさんほど「Funny」を追求している組織と出会ったことがありませんでした。
柳岡さんは、日本で社会課題がなかなか解決しない要因は、「熱狂的なファンの情報発信の仕方」「外から優秀な人が入りにくいことによるイノベーション不足」だと考察しており、その要因に対してキャロットケーキの考え方をもとに、すべての事業で今まで社会課題に関心のなかった人をどのようにして巻き込めるか、楽しく一緒に取り組めるかを重要視してアクションしつづけています。
何よりも柳岡さん自身が楽しみ、明確なビジョンを描いて、仲間と共にアクションしていることがとても伝わってくる時間でした。